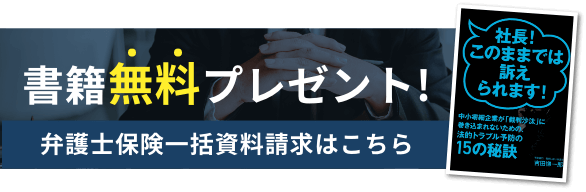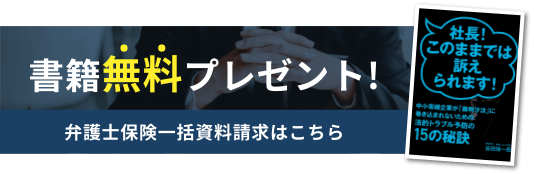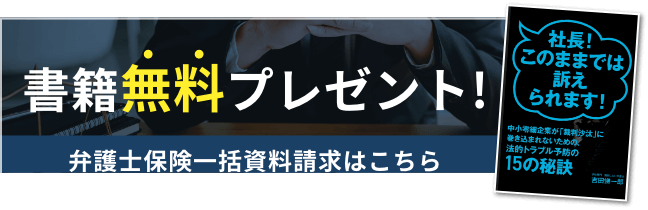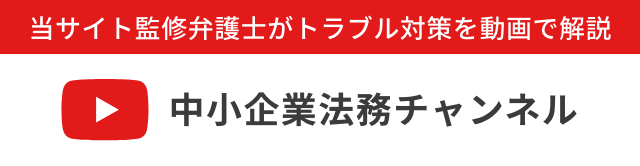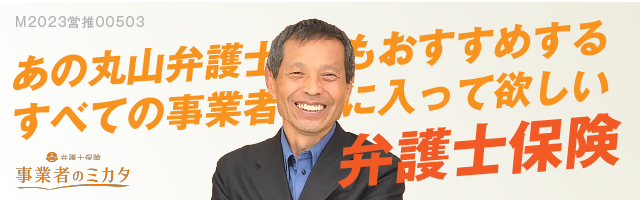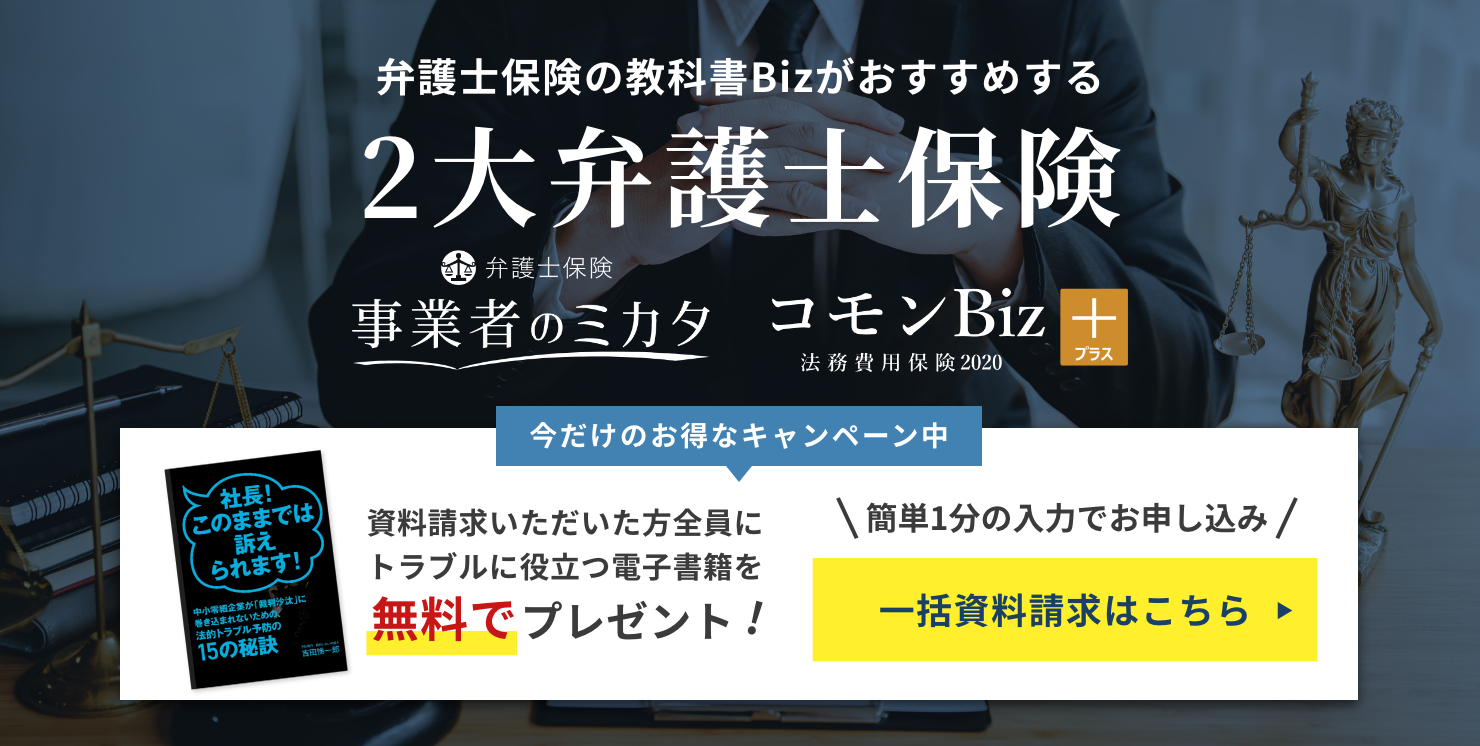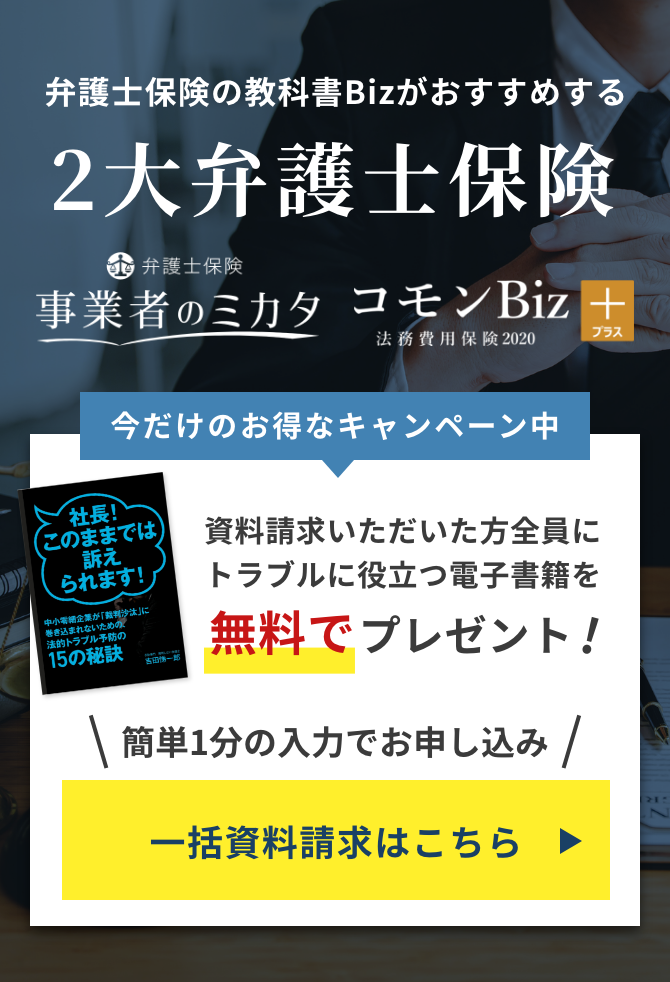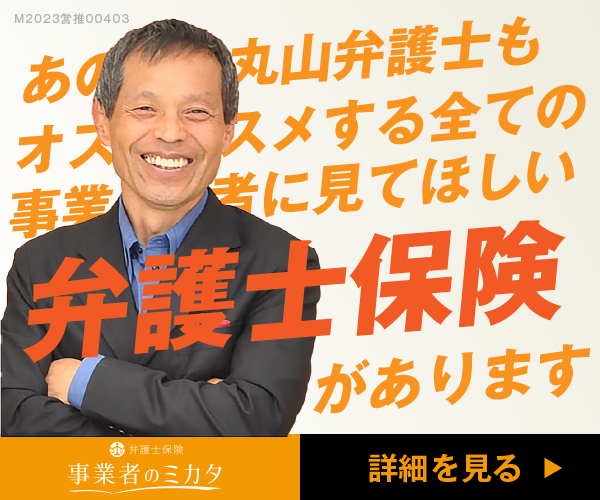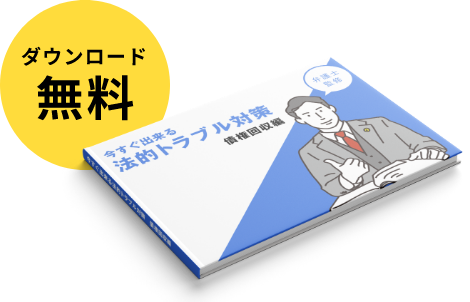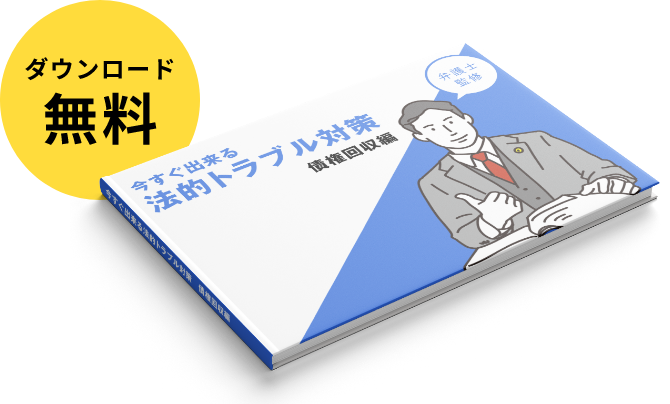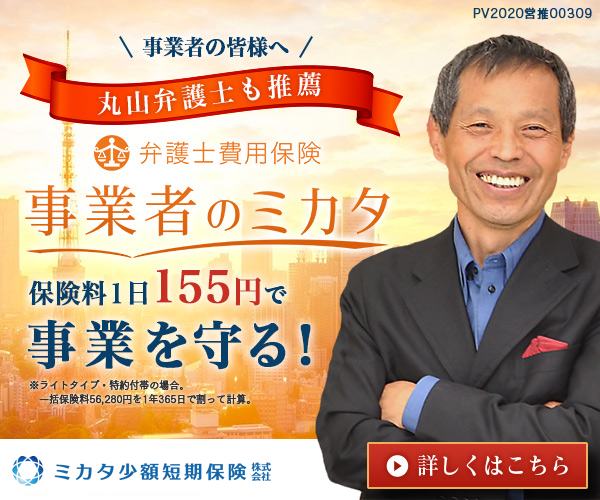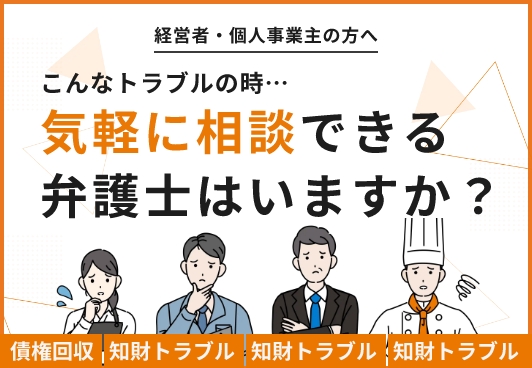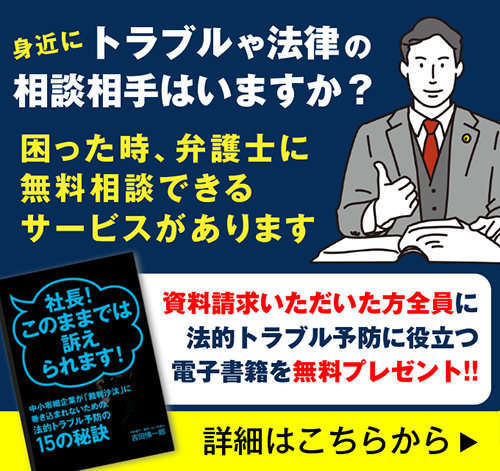債権回収には時効がある?経営者が知っておきたい債権回収の基礎知識
2021年01月21日 2023年05月10日
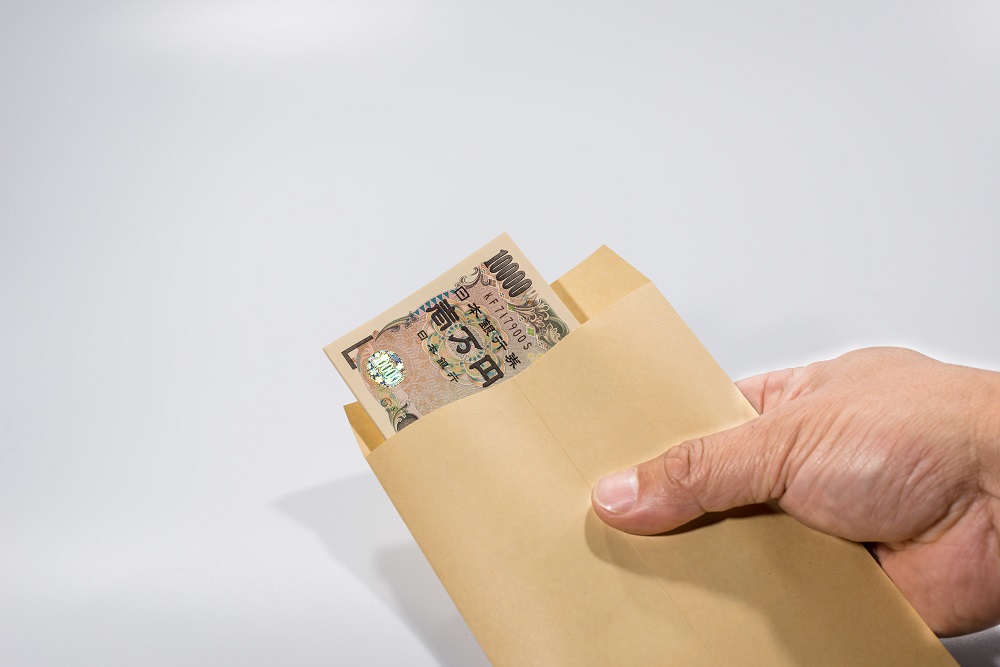
皆さんは「債権」や「債権回収」について意識したことはあるでしょうか。「債権」と聞くとかしこまった法律用語に聞こえるかもしれませんが、普段行っている商取引において発生している身近な権利です。また、この債権には時効があり、債権回収にあたって大きな問題となります。円滑な取引のため、債権や債権回収について知識を深めるのは大切な事です。
今回はそんな「債権」について、おもに債権回収の時効に関して詳しく見ていきましょう。
「債権」とは何か
債権とは、特定の人に対し、特定の行為や給付を請求できる権利のことです。特定の行為や給付とは、金銭の支払いを受けたり、物を受け取ったり、労力の提供を求めたりすることなどが該当します。債権を持つ権利者を、債権者と呼びます。反対に、それら特定の行為や給付を行わなくてはいけない義務を債務といい、債務を負っている者は債務者と呼びます。
たとえば商品を購入した場合、購入した側は商品の引き渡しを請求できる債権者であると同時に、代金の支払いを行わなくてはならない債務者でもあるわけです。こうした契約を「双務契約」と呼びます。
一方、金銭の貸借などにおいては、金銭を返してもらえる債権者と、返す必要のある債務者の関係は一方的です。こうした契約は「片務契約」といいます。
「債権回収」とは、自身の保持している債権に基づき、特定の行為や給付の履行を債務者に要求することを指します。
債権回収には、時効が存在する
債権回収にあたっては、民法に基づき消滅時効が設定されています。一定期間債権を行使しないと、時効が適用されてしまい、債権回収が出来ない事態に陥ります。以下、詳しく見ていきましょう。
時効制度は、①権利の上に眠る者は保護しない②取引の安定性の確保③証拠の散逸などに対する対応、の3つの意味があるものとして説明されます。特に近年では、②取引の安定性の確保に重点が置かれる考え方が一般的です。
具体的な時効の期間については、民法166条において、債権者が
- 権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
- 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
において、債権が消滅すると定められています。
①の「権利を行使することができると知った時」のことを、消滅時効の「主観的起算点」と呼びます。
契約においては、通常、債権者は権利が発生した時点で「自分は権利を行使することができる」と分かっているため、契約上の債権は、5年で時効にかかるのがほとんどであると考えられます。
商取引においては、時効は5年、と覚えておくのがよいでしょう。
一方、②の「権利を行使することができる時」は、消滅時効の「客観的起算点」といいます。客観的起算点に基づくと、権利者が権利を行使できることを知らなくても、時効期間が進行します。
商取引等の契約による債権と異なり、契約とは関係ない債権、例えば事務管理や不当利得によって生じる債権では、主観的起算点と客観的起算点にずれが生じることが多いと考えられます。
客観的起算点における「権利を行使することができる時」とは、権利の行使に法律上の障害がない状態を指す、と考えられています。
主観的起算点と客観的起算点がずれるケースとしては、例えば過払金の返還請求において、まだお金を借りたいと思い取引を続けている最中には、過払金の返還請求が行えることを知っていたとしても、定期的にお金を借りている中で、なかなか過払金返還請求を行うことはできません。こうした場合は、取引が終わってから過払金返還請求権の消滅時効が進行を始める、というのが判例の考え方です。このケースでは、主観的起算点が先に発生し、客観的起算点(取引が終了し、過払金返還請求が行えるようになる時)が後になっています。
債権回収の職業別の時効(参考)
現在の民法は、2017年に改正が行われ、特に本記事で解説している債権の消滅時効について、大きな改正が行われました。改正前の民法では、職業ごとに短期の消滅時効が定められていました。
しかし、適用される範囲が分かりにくい上に、なぜその職業だけ時効が短いのか、疑問に思われるものが少なくありませんでした。
例えば、弁護士の職務に関する債権の消滅時効期間は2年でしたが(改正前民法172条1項)、隣接する職種である公認会計士、税理士、司法書士などには当てはまるのかどうか不透明でした。
そこで、旧民法における職業別の時効は削除され、消滅時効期間は単純化・統一化が図られました。
なお、参考として、短期の消滅時効が定められていた職業は以下の通りです。
【債権の消滅時効:3年】
・医師、助産師又は薬剤師の診療等(170条1項)
・工事の設計、施工又は監理(170条2項)
- 弁護士等の受取書類(171条)
【債権の消滅時効:2年】
・弁護士等の職務(172条)
・生産者、卸売商人又は小売商人の代金(173条1号)
・製作物等(173条2号)
- 学芸又は技能教育の代価(173条3号)
【債権の消滅時効:1年】
・演芸等の報酬(174条2号)
・運送賃(175条3号)
・旅館、料理店、飲食店等(174条4号)
- 動産の損料(174条5号)※損料とは、レンタル料のことです。
時効の完成猶予とは
先に述べた民法改正時に、債権の消滅時効の進行を止めたり、リセットしたりする制度のしくみも変更されました。改正前の民法では、「時効の中断」と定められていたものが、「時効の完成猶予」に改正されたのです。
債権に基づく訴訟を例に考えてみましょう。
訴訟を提起してから、判決が確定する間は、その期間時効が進まないため、完成が猶予されていると言えます。そして、判決が確定すると、そこからまた新たな時効が進行します。これを、改正前民法では「時効の中断」と呼んでいました。
しかしながら、中断と一言に言っても、上記の状況においては、訴訟提起中の「時効の完成猶予」の効果と、判決確定時点の「時効の更新」の効果がそれぞれあり、わかりにくいものでした。
改正後民法では、完成猶予の効果を端的に表す規定になりました。時効の進行がストップする、つまり時効の完成が猶予されている状況と理解すればいいわけです。
また、完成猶予の事由が終了した場合においても、一定期間の猶予を設けています。消滅時効が完成する3カ月前に、債権者が民事訴訟を提起した例で考えてみましょう。債権者が、民事訴訟を提起してから6カ月経過後に訴訟を取り下げた場合には、 「時効の完成猶予の事由」が終了したことになるため、提訴から起算して3カ月後に消滅時効が完成することになります。そこで改正後民法147条1項では、「確定判決又は確定判決と 同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する」までの間は時効の完成は猶予される、と定めています。つまり、訴訟を取り下げてから6カ月を経過するまでは、消滅時効の完成は猶予されることになります。
さらに、改正で「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」が新たに設けられました。先に述べたように、完成猶予の事由の代表的なものには裁判上の請求がありますが、時効が迫ってきた場合は、訴訟を提起しないと時効が完成してしまいます。そうなると、もし訴訟に頼らずに当事者間で話し合いにより解決を試みているケースでも、時効完成をさまたげるために訴訟を提起せざるを得なくなり、当事者双方にとって望ましい状態とは言えません。
そこで、双方の書面による合意により、時効の完成を猶予する制度が設けられました。合意があってから1年間(合意で定めた期間が1年間より短い場合は、その期間)は、時効の完成が猶予されることになります。再度書面による合意がされれば、再び時効の完成が猶予されます。ただし、猶予の期間には制限があり、時効の完成が猶予されなかったとした場合に時効が完成すべき時から、通じて5年を超えることはできません。
いかがでしたでしょうか?費用保険の教科書Bizでは、様々な中小企業・個人事業主の方に役立つ法務情報を弁護士とともに発信しているので、是非他の記事も参考にしてみてください!
こちらの記事もおすすめ
KEYWORDS
- #肖像権
- #施設管理権
- #業務遂行権
- #アルバイト
- #弁護士監修
- #風俗業
- #違約金
- #発信者情報開示請求
- #発信者情報開示命令
- #フリーランス新法
- #フリーランス
- #内容証明
- #臨床法務
- #戦力法務
- #債務不履行
- #威力業務妨害
- #内定
- #始期付解約権留保付労働契約
- #アルハラ
- #法律相談
- #慰謝料
- #知的財産権
- #窃盗罪
- #カスハラ
- #クレーム
- #私文書偽造罪
- #不法行為責任
- #問題社員
- #業務委託
- #時間外労働の上限規制
- #敷金返還請求
- #器物損壊罪
- #電気通信事業者法
- #有線電気通信法
- #電波法
- #迷惑防止条例
- #証拠収集
- #労働安全衛生法
- #弁護士保険
- #事業者のミカタ
- #コロナ
- #LGBT
- #事業継承
- #起業
- #マタハラ
- #解雇
- #M&A
- #借地借家法
- #サブリース
- #風評被害
- #情報開示請求
- #特定電気通信
- #自己破産
- #破産法
- #別除権
- #外国人労働者
- #セクハラ
- #ハラスメント
- #時効
- #個人情報保護法
- #サブリース契約
- #共同不法行為
- #外国人雇用
- #競業避止義務
- #退職金
- #職業選択の自由
- #弁護士
- #下請法
- #事件
- #過労死
- #注意義務違反
- #労働基準法
- #解雇権
- #不当解雇
- #著作権
- #フリー素材
- #契約書
- #業務委託契約
- #再委託
- #Web制作
- #デイサービス
- #訪問介護
- #老人ホーム
- #動画解説
- #定期建物賃貸借
- #定期賃貸借契約
- #損害賠償
- #不法行為
- #使用者責任
- #雇用
- #障害者差別解消法
- #差別
- #障害者
- #パワハラ
- #少額訴訟
- #裁判
- #破産
- #債権回収
- #交通事故
- #労災
- #内定取り消し
- #留保解約権
- #景品表示法
- #薬機法
- #家賃交渉
- #フランチャイズ
- #うつ病
- #未払い
- #遺失物等横領罪
- #無断キャンセル
- #業務上横領罪
- #誹謗中傷
- #賃貸借契約
- #家賃未払い
- #立ち退き
- #判例
- #就業規則
- #有給休暇
- #クレーマー
- #残業
- #入店拒否
- #予防法務
- #顧問弁護士
- #健康診断
- #個人情報
RANKING
-
01
【弁護士監修】相手に許可のない録音・盗撮は違法? 電話や会話の証拠を録音・録画する方法と機器を紹介
-
02
免責事項と注意事項は何が違う? その効力から職業別の例文までわかりやすく紹介。
-
03
【弁護士監修】少額訴訟のメリット・デメリットとは。費用・必要書類から手続きの流れまでを解説。
-
04
無断駐車への張り紙や罰金は有効? 無断駐車の対策と対応、してはいけないこと。
-
05
【弁護士監修】客を選ぶ権利は法律に存在する? 入店拒否・出禁が違法になる場合とは。
-
06
【弁護士監修】店舗スタッフの無断撮影は違法?経営者が知っておくべき肖像権・業務遂行権の侵害リスクと対応
-
07
【弁護士監修】外国人お断りは違法? インバウンドブームに潜む外国人旅行客とのトラブルと対策
-
08
クレジットカードや自動車保険の弁護士保険は使えない!? 補償される範囲をチェックして弁護士保険を比較・検討しよう。
-
09
著作権侵害を防ぐために意識したい4つのこと(経営者向け)
-
10
フリーランス・個人事業主が知っておきたい労働基準法の考え方と適用される要件
動画で学ぶ!
事業者向け法律知識
同じカテゴリの記事
KEYWORDS
- #肖像権
- #施設管理権
- #業務遂行権
- #アルバイト
- #弁護士監修
- #風俗業
- #違約金
- #発信者情報開示請求
- #発信者情報開示命令
- #フリーランス新法
- #フリーランス
- #内容証明
- #臨床法務
- #戦力法務
- #債務不履行
- #威力業務妨害
- #内定
- #始期付解約権留保付労働契約
- #アルハラ
- #法律相談
- #慰謝料
- #知的財産権
- #窃盗罪
- #カスハラ
- #クレーム
- #私文書偽造罪
- #不法行為責任
- #問題社員
- #業務委託
- #時間外労働の上限規制
- #敷金返還請求
- #器物損壊罪
- #電気通信事業者法
- #有線電気通信法
- #電波法
- #迷惑防止条例
- #証拠収集
- #労働安全衛生法
- #弁護士保険
- #事業者のミカタ
- #コロナ
- #LGBT
- #事業継承
- #起業
- #マタハラ
- #解雇
- #M&A
- #借地借家法
- #サブリース
- #風評被害
- #情報開示請求
- #特定電気通信
- #自己破産
- #破産法
- #別除権
- #外国人労働者
- #セクハラ
- #ハラスメント
- #時効
- #個人情報保護法
- #サブリース契約
- #共同不法行為
- #外国人雇用
- #競業避止義務
- #退職金
- #職業選択の自由
- #弁護士
- #下請法
- #事件
- #過労死
- #注意義務違反
- #労働基準法
- #解雇権
- #不当解雇
- #著作権
- #フリー素材
- #契約書
- #業務委託契約
- #再委託
- #Web制作
- #デイサービス
- #訪問介護
- #老人ホーム
- #動画解説
- #定期建物賃貸借
- #定期賃貸借契約
- #損害賠償
- #不法行為
- #使用者責任
- #雇用
- #障害者差別解消法
- #差別
- #障害者
- #パワハラ
- #少額訴訟
- #裁判
- #破産
- #債権回収
- #交通事故
- #労災
- #内定取り消し
- #留保解約権
- #景品表示法
- #薬機法
- #家賃交渉
- #フランチャイズ
- #うつ病
- #未払い
- #遺失物等横領罪
- #無断キャンセル
- #業務上横領罪
- #誹謗中傷
- #賃貸借契約
- #家賃未払い
- #立ち退き
- #判例
- #就業規則
- #有給休暇
- #クレーマー
- #残業
- #入店拒否
- #予防法務
- #顧問弁護士
- #健康診断
- #個人情報
RANKING
-
01
【弁護士監修】相手に許可のない録音・盗撮は違法? 電話や会話の証拠を録音・録画する方法と機器を紹介
-
02
免責事項と注意事項は何が違う? その効力から職業別の例文までわかりやすく紹介。
-
03
【弁護士監修】少額訴訟のメリット・デメリットとは。費用・必要書類から手続きの流れまでを解説。
-
04
無断駐車への張り紙や罰金は有効? 無断駐車の対策と対応、してはいけないこと。
-
05
【弁護士監修】客を選ぶ権利は法律に存在する? 入店拒否・出禁が違法になる場合とは。
-
06
【弁護士監修】店舗スタッフの無断撮影は違法?経営者が知っておくべき肖像権・業務遂行権の侵害リスクと対応
-
07
【弁護士監修】外国人お断りは違法? インバウンドブームに潜む外国人旅行客とのトラブルと対策
-
08
クレジットカードや自動車保険の弁護士保険は使えない!? 補償される範囲をチェックして弁護士保険を比較・検討しよう。
-
09
著作権侵害を防ぐために意識したい4つのこと(経営者向け)
-
10
フリーランス・個人事業主が知っておきたい労働基準法の考え方と適用される要件
動画で学ぶ!
事業者向け法律知識