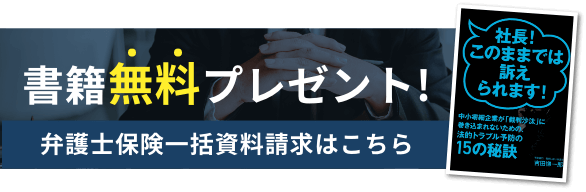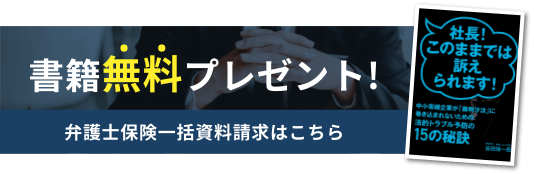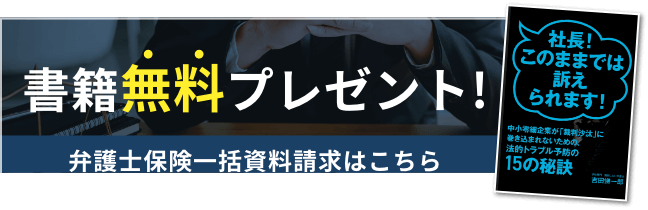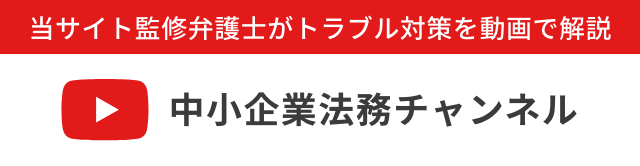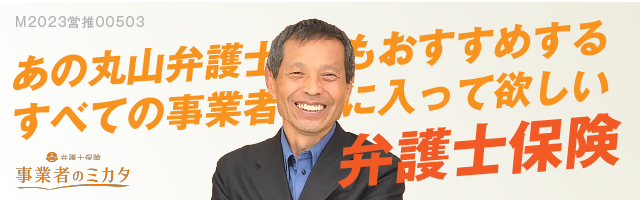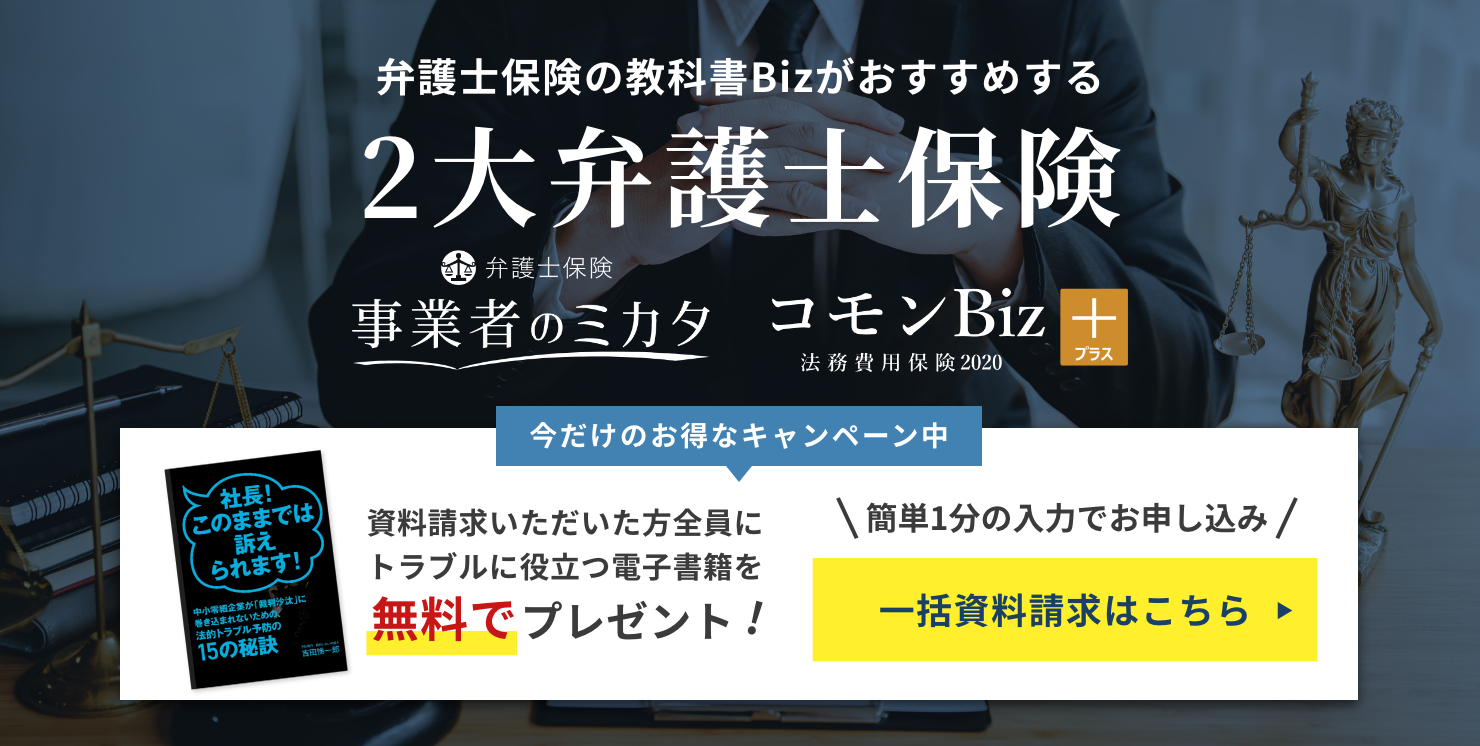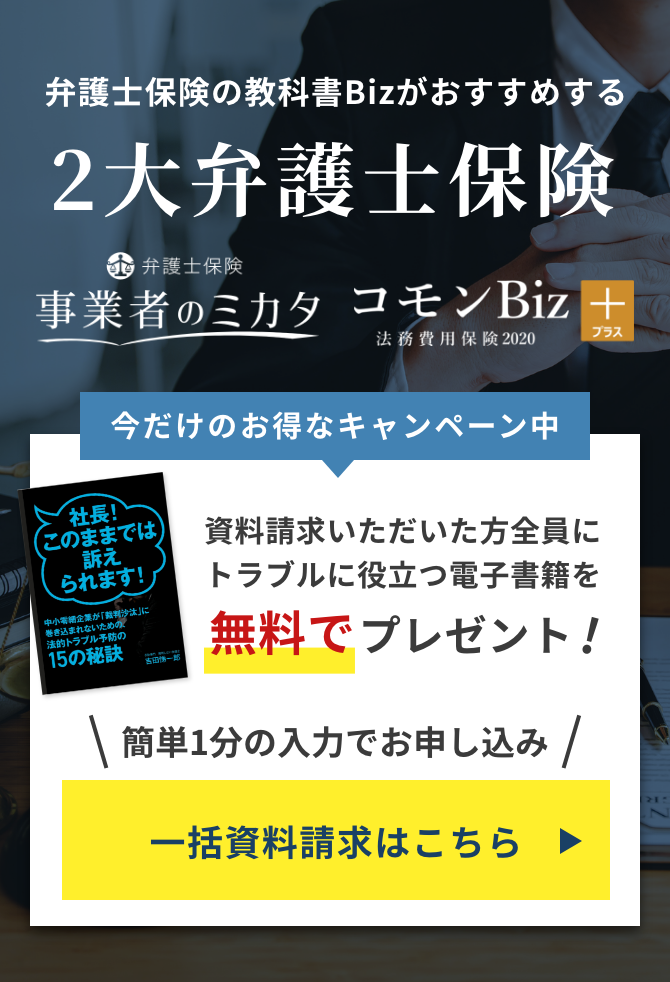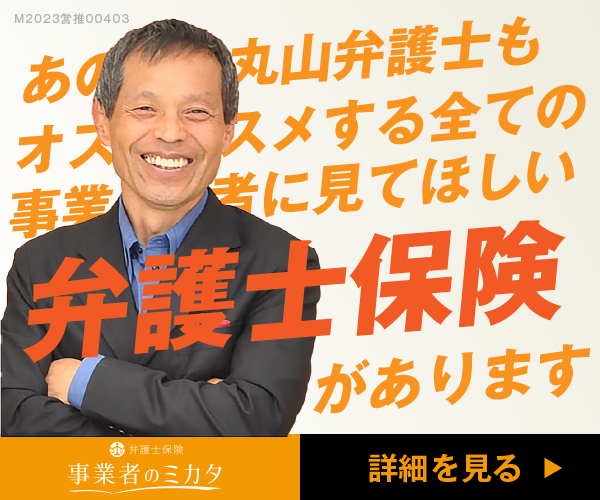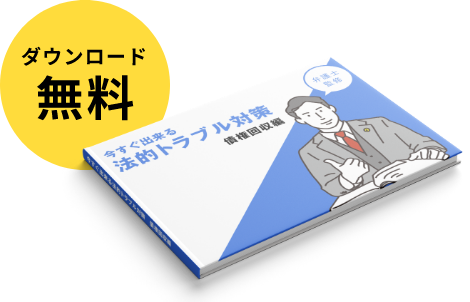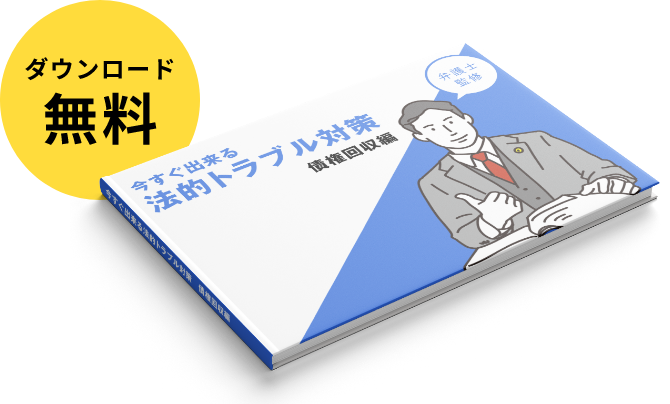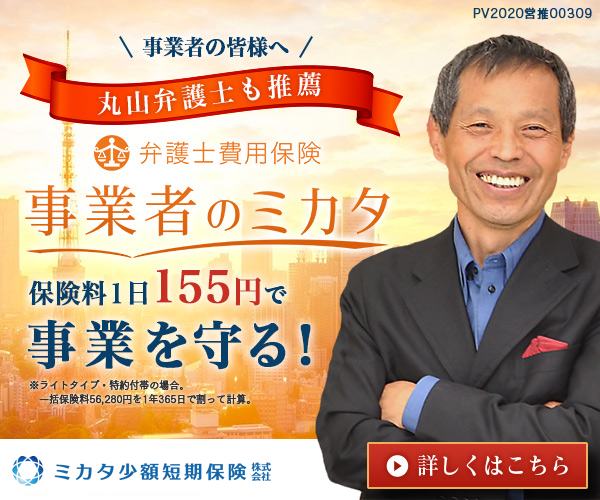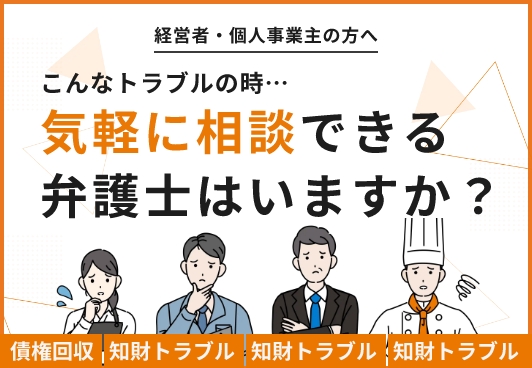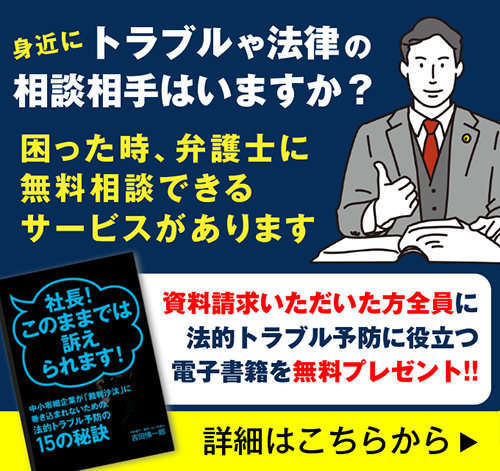【弁護士監修】店舗スタッフの無断撮影は違法?経営者が知っておくべき肖像権・業務遂行権の侵害リスクと対応
2025年04月14日 2025年11月12日
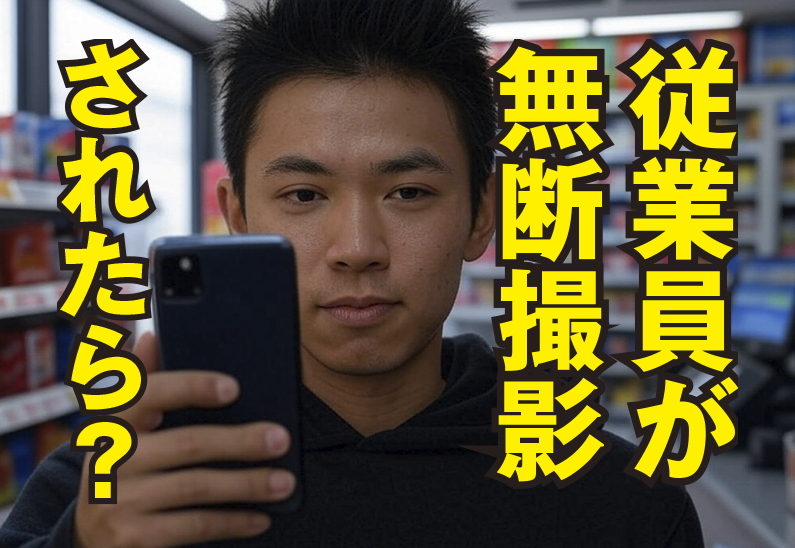
近年、SNSの普及に伴い、店舗スタッフや会社の従業員が無断で撮影され、そのままネット上に晒されるトラブルが増加しています。いわゆる“晒し動画”や“クレーム動画”として拡散されることで、本人だけでなく企業側にも大きなダメージを与えるケースが後を絶ちません。
「自分は悪くない」「この店員の態度が悪い」と一方的な主張とともに撮影・投稿する行為は、現場の従業員の士気低下や離職リスクにも直結し、企業イメージの毀損にもつながりかねません。
今回は、「スタッフ・従業員の無断撮影」が法律上どのような問題をはらむのかを、肖像権や業務遂行権といった法的観点からわかりやすく解説します。
スマホで店員を無断撮影することの違法性
従業員が制止しているにも関わらず無断で写真や動画を撮影する行為は、肖像権の侵害になります。また、企業・店舗側の業務を妨害するとして「業務遂行権」の侵害にもなりますし、企業・店舗には自らの施設内部の事柄は自由に決められますので「施設管理権」の侵害にあたる可能性もあります。場合によっては違法行為と判断され、損害賠償請求の対象となることも十分に考えられます。
肖像権の侵害
肖像権とは、本人の許可なくその容貌を撮影・公開されない権利のことです。法令に明確な条文は存在しないものの、肖像権侵害は民法709条の不法行為に該当し、判例も「みだりにその容貌・姿態を撮影されない権利」として認めています。特に、店舗スタッフや従業員の顔や姿を、本人の同意なく撮影・SNS等で公開した場合、プライバシー権や人格権の侵害に該当し、法的責任を問われるリスクが生じます。権利侵害が認められた場合は慰謝料などの損害賠償請求の対象となります。
さらに、撮影した動画や画像をSNSなどで「悪質店」などと誹謗中傷目的で投稿した場合は、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)などにも発展する可能性があります。
| TIPS 後からモザイクをかければ大丈夫? |
|---|
| 本稿の件に限れば「被撮影者が制止しているにも関わらず無断で撮影」が焦点となっているため、モザイクをかけてもかけなくても撮影すること自体が肖像権の侵害に該当します。ただし、例えば街の様子を撮影してて映り込んでしまった通行人などは撮影する分には問題ございませんが、そのままSNSなどにアップロードすると肖像権の侵害に該当する可能性があるため、モザイクをかけたほうがいいでしょう。 |
業務遂行権・施設管理権の侵害
従業員は、雇用契約のもと業務に従事しており、企業・店舗側には安全かつ円滑に業務を遂行させる権利(業務遂行権)が認められます。無断撮影によって業務が妨害されれば、その権利が侵害されたとして、店舗側から損害賠償請求や退店要求が可能です。
また、店舗内は原則として施設管理権者(店側)がルールを決めることができ、「無断撮影禁止」などのルールを設けている場合、その違反行為は不法行為(民法709条)に該当し、排除・警告・通報など正当な対応が法的に認められます。
撮影者は「犯罪」に問われるケースも
加えて、スマホでの無断撮影は状況によっては刑事事件に発展することもあります。以下のようなケースでは刑法に抵触する可能性があるため、非常に危険です。
| 想定される違反行為 | 該当する可能性のある罪名 | 内容 |
|---|---|---|
| 撮影の強行 | 強要罪(刑法223条) | 店側の制止を無視し撮影を強行した場合 |
| 執拗な撮影・待ち伏せ | ストーカー規制法違反 | 店員個人を執拗に狙った場合 |
| ネット投稿での中傷 | 名誉毀損罪(刑法230条) | 店舗や従業員の社会的評価を害した場合 |
店員が無断撮影された場合にするべきこと
万が一、店員や従業員が無断で撮影される場面に遭遇した場合、店舗や企業側は適切かつ冷静に対応する必要があります。ここでは、現場対応とその後の対応に分けて、具体的な対策を解説します。
【現場対応】無断撮影をされた場合の初動対応
1.速やかに撮影者へ「撮影中止」を明確に伝える
無断撮影をする客は大きく分けて「悪気なく当たり前のようにやってる」か「悪質なクレーマー」場合が多いです。後者の場合は、強気に伝えるとさらにヒートアップする可能性があるため、まずは落ち着いた口調で、「許可のない撮影はご遠慮いただいております」「無断撮影はお控えください」と伝えましょう。
もしも、従業員がそのようなトラブルに見舞われている場面を発見したら、責任者は速やかに対応に入りましょう。また、すでに無断撮影されてしまっている場合は、写真の削除を求めましょう。
2.施設内の「撮影禁止」ルールを根拠として伝える
店舗ルールや施設管理権に基づく禁止事項であることを説明し、用意しているのであれば「店内では撮影禁止とさせていただいております」と掲示内容を示せると最善です。
3.悪質な場合は、撮影者に対し「退店要求」や「警察への通報」も検討
撮影をやめず業務妨害が続く場合は、毅然とした態度で退店を求めましょう。もしそれでも暴言・威圧的行為があれば、その場で110番通報も正当な対応となります。
| TIPS 強制的な行為はしないように! |
|---|
| 撮影者のカメラを取り上げるなどといった強制的な措置を取ろうとした場合、過度な実力行使をする必要があることが多く、そうなった場合今度は従業員側が加害者になる可能性が出てきます。そのため、冷静な対応をするように心がけましょう。 |
【その後の対応】被害拡大を防ぐためのポイント
1.撮影の事実・状況を速やかに記録する(証拠化)
無断撮影が発生した場合、撮影の日時・状況・相手の特徴などを詳細に記録し、可能であれば防犯カメラ映像なども別に残しておくようにしましょう。また場合によっては、無断撮影している状態を録画することも法的には正当にはなりますが、ヒートアップする可能性もありますので、慎重に判断しましょう。
2.上長・本部への報告・共有
企業としての統一対応を図るため、必ず責任者へ撮影があった事実を共有します。責任者は最悪を想定して、法務部や顧問弁護士にも事実共有をしておきましょう。
3.SNSの監視・対応
無断撮影が発生した場合、SNS(XやInstgramだけでなくTikTokやYouTubeなどの動画サイトも)にアップロードされている可能性もあります。店舗名や地名、「イタリアン」「コンビニ」などの業種名なども含めて検索をかけて、もしもアップロードされていたら速やかに会社名義で削除要請をしましょう。
4.法的措置
3でアップロードされて、削除要請に応じてもらえなかったり、最悪の場合は拡散されて店舗の風評被害や従業員の誹謗中傷に発展したりするケースも出てきます。そうなった場合は、速やかに弁護士に相談して法的な削除要請と同時に損害賠償請求や刑事告訴も視野に入れて動く必要があります。
5.事後対応
削除をしてもらったからと言って終わりではありません。必ず投稿者本人から投稿に対する謝罪文、事実の訂正文などを声明を出してもらい、信頼の回復を図るようにしましょう。その際は、無断撮影禁止の周知もしておくといいでしょう。
無断撮影を予防するための対策
無断撮影によるトラブルは、発生後の対応だけでなく事前の予防策が非常に重要です。店舗や企業側が適切な対策を講じることで、トラブルの発生率を大きく下げることができます。
店内掲示による「無断撮影禁止」の明示
店内の目立つ場所に「無断撮影禁止」の掲示を設置することで、利用者への明確なルール周知になります。例えば以下のような例文が標準的です。
- 店舗内での写真・動画撮影はご遠慮ください。
- スタッフや他のお客様の無断撮影・SNS等への投稿は固くお断りいたします。
特にレジ周り、出入口、各テーブルなど撮影が行われやすい場所への掲示が効果的で、準備が難しい場合はAmazonなどのショッピングサイトで購入することも可能です。
利用規約や店内ルールへの明記
WebサイトやSNSなどがある場合は店舗の利用規約や注意事項にも「無断撮影禁止」「撮影は許可制」と明記しておくことで、トラブル発生時に法的根拠となり得ます。
防犯カメラ設置による抑止効果
店内に防犯カメラを設置し、「防犯カメラ作動中」の表示を出すことで無断撮影や迷惑行為の抑止力が期待できます。あわせて、万が一トラブルが発生した際の証拠保全にもなります。もしも予算の関係上設置が難しい場合はダミーカメラなどでも一定の効果が見込めます。
弁護士が付いていることを予見させる

弁護士保険に加入している場合は弁護士保険加入ステッカーをもらえる商品が多いです。これらのステッカーをレジなど目につきやすい場所に掲示しておくことで無断撮影の抑止効果が見込めます。
実際の判例・裁判例から見る「無断撮影・肖像権侵害」
船橋市役所・クレーマー無断撮影事件
千葉県船橋市役所の生活保護担当窓口において、男性来庁者が職員の対応に不満を持ち、職員を無断で撮影してその動画を「船橋市および千葉県警の実態」などのタイトルでYouTubeに計65本投稿しました。動画内では職員に対し「おまえらみたいなばかを写す義務がある」などと暴言を吐く場面もあり、職員や他の来庁者とのトラブルに発展していました。船橋市は市庁舎管理規則で庁舎内での無許可撮影を禁止しており、度重なる注意にも従わないため、この男性を相手取り無断撮影の差し止めを求め提訴しました。
判決・結末
千葉地裁令和2年6月25日判決。千葉地方裁判所は、市の主張を一部認め、庁舎管理者の許可なく市庁舎内で撮影することの禁止(無断撮影差止め)を命じる判決を言い渡しました。裁判所は「被告の一連の撮影行為は権利行使の範囲を明らかに超えており、市の業務に及ぼす支障の程度が著しい」と判断し、市側の施設管理権に基づく差止め請求を認容しました。なお全面的・無条件の差止めは棄却されましたが、「庁舎管理者の許可なく」という条件付きで差止めを認めています。
もしもの無断撮影に備えて
このように、無断撮影は企業の評判や従業員の安全を脅かす危険性を含んでいます。それは避けようと思っても避けられるものではありません。そのため、無断撮影の事案が発生した場合、速やかに弁護士に相談することが理想です。しかし、いざ弁護士を使うとなると「誰に相談したらいいかわからない」「費用が高そう」「裁判って難しそう」などいろいろな不安や心配から泣き寝入りしてしまう方も多いです。そこでおすすめなのが弁護士保険になります。
弁護士保険に入るメリット
1.トラブルに発展する前に予防できる
弁護士保険に加入すると、前述でも消化した弁護士保険加入者証や弁護士保険加入ステッカーがもらえます。これを提示することで「こちらはいつでも弁護士を使える」という姿勢を相手に伝えることでトラブルに発展する前の抑止力となります。
2.弁護士への電話相談が無料で出来る
弁護士のへの電話相談が無料で行えるといった付帯サービスが付いてきます。トラブルの概要を話し、そこからどう動くのが最善かを法律の専門家からアドバイスしてもらえます。
3.弁護士費用・裁判費用が補償される
それでも解決できずに訴訟などに発展したとしても、一般的に弁護士を使った時にかかる着手金や訴訟費用は保険で賄われますので高額な出費を恐れる心配がありません。
他にも多くのメリットがありますので詳しく知りたい方は以下のリンクをご覧ください。
KEYWORDS
- #肖像権
- #施設管理権
- #業務遂行権
- #アルバイト
- #弁護士監修
- #風俗業
- #違約金
- #発信者情報開示請求
- #発信者情報開示命令
- #フリーランス新法
- #フリーランス
- #内容証明
- #臨床法務
- #戦力法務
- #債務不履行
- #威力業務妨害
- #内定
- #始期付解約権留保付労働契約
- #アルハラ
- #法律相談
- #慰謝料
- #知的財産権
- #窃盗罪
- #カスハラ
- #クレーム
- #私文書偽造罪
- #不法行為責任
- #問題社員
- #業務委託
- #時間外労働の上限規制
- #敷金返還請求
- #器物損壊罪
- #電気通信事業者法
- #有線電気通信法
- #電波法
- #迷惑防止条例
- #証拠収集
- #労働安全衛生法
- #弁護士保険
- #事業者のミカタ
- #コロナ
- #LGBT
- #事業継承
- #起業
- #マタハラ
- #解雇
- #M&A
- #借地借家法
- #サブリース
- #風評被害
- #情報開示請求
- #特定電気通信
- #自己破産
- #破産法
- #別除権
- #外国人労働者
- #セクハラ
- #ハラスメント
- #時効
- #個人情報保護法
- #サブリース契約
- #共同不法行為
- #外国人雇用
- #競業避止義務
- #退職金
- #職業選択の自由
- #弁護士
- #下請法
- #事件
- #過労死
- #注意義務違反
- #労働基準法
- #解雇権
- #不当解雇
- #著作権
- #フリー素材
- #契約書
- #業務委託契約
- #再委託
- #Web制作
- #デイサービス
- #訪問介護
- #老人ホーム
- #動画解説
- #定期建物賃貸借
- #定期賃貸借契約
- #損害賠償
- #不法行為
- #使用者責任
- #雇用
- #障害者差別解消法
- #差別
- #障害者
- #パワハラ
- #少額訴訟
- #裁判
- #破産
- #債権回収
- #交通事故
- #労災
- #内定取り消し
- #留保解約権
- #景品表示法
- #薬機法
- #家賃交渉
- #フランチャイズ
- #うつ病
- #未払い
- #遺失物等横領罪
- #無断キャンセル
- #業務上横領罪
- #誹謗中傷
- #賃貸借契約
- #家賃未払い
- #立ち退き
- #判例
- #就業規則
- #有給休暇
- #クレーマー
- #残業
- #入店拒否
- #予防法務
- #顧問弁護士
- #健康診断
- #個人情報
RANKING
-
01
【弁護士監修】相手に許可のない録音・盗撮は違法? 電話や会話の証拠を録音・録画する方法と機器を紹介
-
02
免責事項と注意事項は何が違う? その効力から職業別の例文までわかりやすく紹介。
-
03
【弁護士監修】店舗スタッフの無断撮影は違法?経営者が知っておくべき肖像権・業務遂行権の侵害リスクと対応
-
04
無断駐車への張り紙や罰金は有効? 無断駐車の対策と対応、してはいけないこと。
-
05
【弁護士監修】客を選ぶ権利は法律に存在する? 入店拒否・出禁が違法になる場合とは。
-
06
【弁護士監修】少額訴訟のメリット・デメリットとは。費用・必要書類から手続きの流れまでを解説。
-
07
敷地内で客に嘔吐された時に飲食店がするべき清掃処理手順と法的な注意点
-
08
キャンセル料は取れる? 予約の無断キャンセル(ノーショー)問題の対策と法律を学ぶ
-
09
店で泥酔した客が暴れたら損害賠償は取れる? 酔客トラブルの予防と対処法
-
10
恋愛禁止は違法? アイドルを始める際に気をつけたい契約内容を解説
動画で学ぶ!
事業者向け法律知識
同じカテゴリの記事
KEYWORDS
- #肖像権
- #施設管理権
- #業務遂行権
- #アルバイト
- #弁護士監修
- #風俗業
- #違約金
- #発信者情報開示請求
- #発信者情報開示命令
- #フリーランス新法
- #フリーランス
- #内容証明
- #臨床法務
- #戦力法務
- #債務不履行
- #威力業務妨害
- #内定
- #始期付解約権留保付労働契約
- #アルハラ
- #法律相談
- #慰謝料
- #知的財産権
- #窃盗罪
- #カスハラ
- #クレーム
- #私文書偽造罪
- #不法行為責任
- #問題社員
- #業務委託
- #時間外労働の上限規制
- #敷金返還請求
- #器物損壊罪
- #電気通信事業者法
- #有線電気通信法
- #電波法
- #迷惑防止条例
- #証拠収集
- #労働安全衛生法
- #弁護士保険
- #事業者のミカタ
- #コロナ
- #LGBT
- #事業継承
- #起業
- #マタハラ
- #解雇
- #M&A
- #借地借家法
- #サブリース
- #風評被害
- #情報開示請求
- #特定電気通信
- #自己破産
- #破産法
- #別除権
- #外国人労働者
- #セクハラ
- #ハラスメント
- #時効
- #個人情報保護法
- #サブリース契約
- #共同不法行為
- #外国人雇用
- #競業避止義務
- #退職金
- #職業選択の自由
- #弁護士
- #下請法
- #事件
- #過労死
- #注意義務違反
- #労働基準法
- #解雇権
- #不当解雇
- #著作権
- #フリー素材
- #契約書
- #業務委託契約
- #再委託
- #Web制作
- #デイサービス
- #訪問介護
- #老人ホーム
- #動画解説
- #定期建物賃貸借
- #定期賃貸借契約
- #損害賠償
- #不法行為
- #使用者責任
- #雇用
- #障害者差別解消法
- #差別
- #障害者
- #パワハラ
- #少額訴訟
- #裁判
- #破産
- #債権回収
- #交通事故
- #労災
- #内定取り消し
- #留保解約権
- #景品表示法
- #薬機法
- #家賃交渉
- #フランチャイズ
- #うつ病
- #未払い
- #遺失物等横領罪
- #無断キャンセル
- #業務上横領罪
- #誹謗中傷
- #賃貸借契約
- #家賃未払い
- #立ち退き
- #判例
- #就業規則
- #有給休暇
- #クレーマー
- #残業
- #入店拒否
- #予防法務
- #顧問弁護士
- #健康診断
- #個人情報
RANKING
-
01
【弁護士監修】相手に許可のない録音・盗撮は違法? 電話や会話の証拠を録音・録画する方法と機器を紹介
-
02
免責事項と注意事項は何が違う? その効力から職業別の例文までわかりやすく紹介。
-
03
【弁護士監修】店舗スタッフの無断撮影は違法?経営者が知っておくべき肖像権・業務遂行権の侵害リスクと対応
-
04
無断駐車への張り紙や罰金は有効? 無断駐車の対策と対応、してはいけないこと。
-
05
【弁護士監修】客を選ぶ権利は法律に存在する? 入店拒否・出禁が違法になる場合とは。
-
06
【弁護士監修】少額訴訟のメリット・デメリットとは。費用・必要書類から手続きの流れまでを解説。
-
07
敷地内で客に嘔吐された時に飲食店がするべき清掃処理手順と法的な注意点
-
08
キャンセル料は取れる? 予約の無断キャンセル(ノーショー)問題の対策と法律を学ぶ
-
09
店で泥酔した客が暴れたら損害賠償は取れる? 酔客トラブルの予防と対処法
-
10
恋愛禁止は違法? アイドルを始める際に気をつけたい契約内容を解説
動画で学ぶ!
事業者向け法律知識